
心理学でひも解く幸せのメカニズム
幸福学入門
- 受講期間:3か月
- 受講料:19,910円
受講対象者:全社員
-
先行きが見えないVUCAの時代、
「これが私の幸せ」。
そう言える人はきっと強い。
-
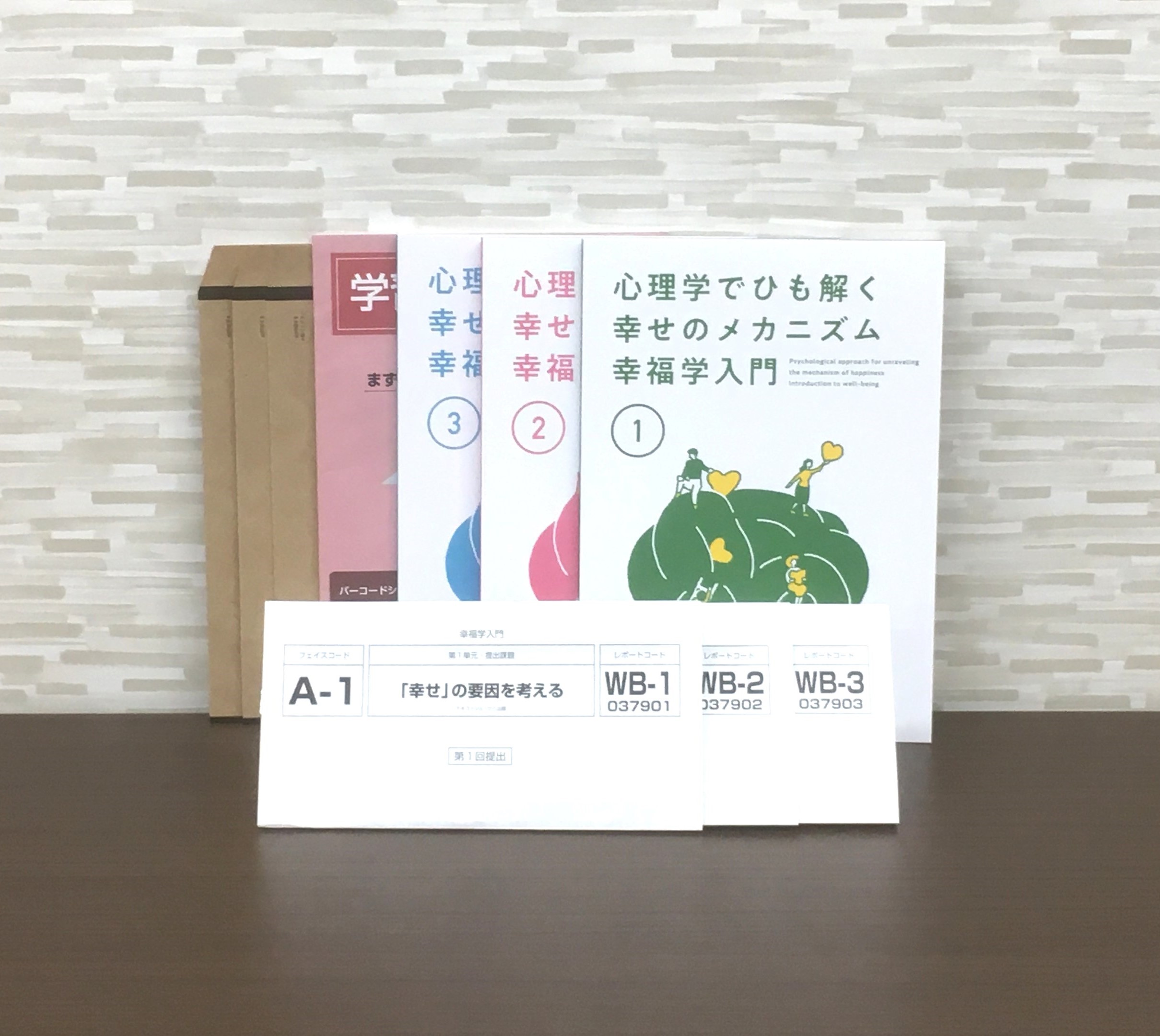
学習のねらいと講座の特徴
- ●「これが私の幸せ」。そう言える人はきっと強い。
-
幸福学の「幸せ」は認知科学、心理学、医学などの分野を統合した学術的なアプローチで可能にする心身の健康、“well-being”(ウェルビーイング)です。
Well-beingという言葉が使われ始めたのは1946年の世界保健機関設立時ですが、近年日本でも、働き方改革でワークライフ・バランスの大切さが見直されたり、新型コロナウィルスの影響で改めて「幸福」について考える機会が増えたりして、物理的な豊かさ=幸せ、の方程式が崩れつつあります。一人ひとりの生き方が多様化し、自由度が高まっている一方で、「こうしたら幸せになれる」という絶対的な正解もありません。
本講座では、心理学や認知のメカニズムを活用し、「幸せの4つの因子」を学ぶことで自分の幸せの「軸」をみつけることを目指します。自分が何を大切にし、何を幸せとするのかを再確認することは、先行きがみえないこれからの時代で、確かな強みになるはずです。
- ●世界が注目する「幸福」(well-being)を
-
現在、 “Well-being”という概念は世界中で注目され、人々の「幸福度」を高めることはSDGsのターゲットの1つになっています。
また、ニュージーランド政府は国家予算に「幸せ」のコンセプトを導入したり、アイスランド首相がGDPに代わる幸福度の指標を掲げたりと、世界各国で「幸福度」が注目され、国の発展度の指標にすることが検討されています。
政界だけでなく企業でも、より良い組織運営を行うために、well-being が必要不可欠な要素であると認知されているようです。
幸福度を上げることは個人としてはもちろん、生産性向上や福利厚生につながるため組織としても重視するべきポイントです。
本講座では、宗教や哲学的な「幸せ=Happiness」とは異なり、社会福祉の立場からアカデミックに幸福を考える学問としての「幸福学」を学び、自身のこれからの人生に、簡単ですぐに取り入れられる考え方やフレームワークを多く紹介しています。
- ● 受講特典:『自己発見テスト Pazz』
- IECの通信教育を受講いただいた方には、『自己発見テスト Pazz』のチャレンジ権を無料でお贈りしています。
Pazz(パズ)とは、仕事に大切な24のチカラを見える化する自己発見テストです。 Web上に用意された75の質問に答えることによって、自分が現在、どのような特性があるのかを確認することができます。 15分ほどで終わるので、今後の学習のヒントにするためにも、ぜひPazzにトライしてみてください!
https://iec.co.jp/pazz/ -
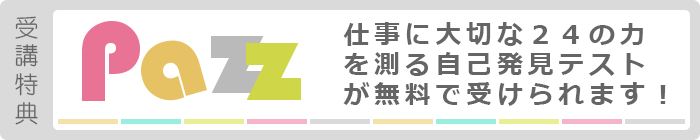
講座カリキュラム
1か月目
「幸福」を学問として考える
人生と仕事に役立つ「幸福学」とは/成熟社会で必要な幸せの価値観とは?/幸福感のジェネレーションギャップ/「幸せ」とは何か/長続きする幸せと長続きしない幸せ/「幸せ」はコントロールできる/幸せは多様だがメカニズムはシンプル/幸せは脳の活動に支配されている/「幸せ」になることはダイエットに似ている/他
2か月目
「幸せの4つの因子」の
メカニズムを学ぶ
「幸せ」になるために必要なこと/自分自身の「幸せ度」を測定してみる/「幸せ」になる方法/「 幸せの4つの因子」とは?/「幸せの法則」とは?/「やってみよう!因子」を伸ばす/グローバル・ネットワーク社会での自己実現/「ありがとう!因子」を伸ばす/多様な友人を持ち人とのつながりを広げる/〇×カレンダー法/他
3か月目
自分自身の幸せを再確認する
「なんとかなる!因子」を伸ばす/前向きと楽観性が幸福感を高める理由/「 メタ認知力」で自分を変える/「ありのままに!因子」を伸ばす/独立と自分らしさの因子を伸ばす/ふつうの人ではなく「変人」を目指す「幸せな人」になるために/「画一的」から脱け出す/幸せのパターンを確認する/他
教材構成 テキスト3冊、提出課題3回
